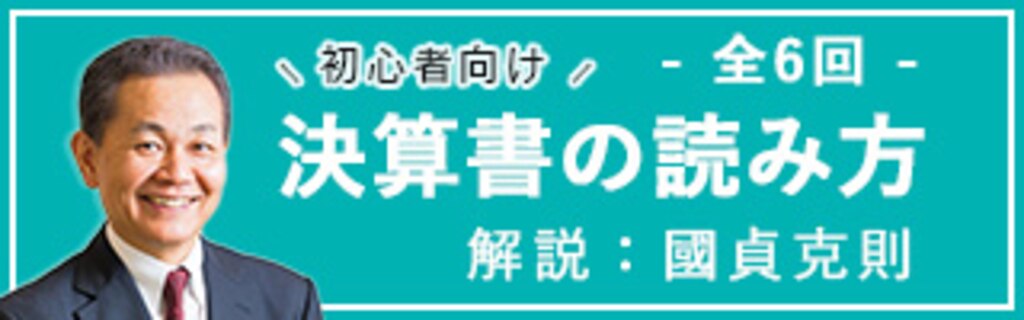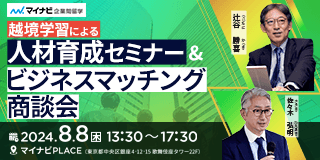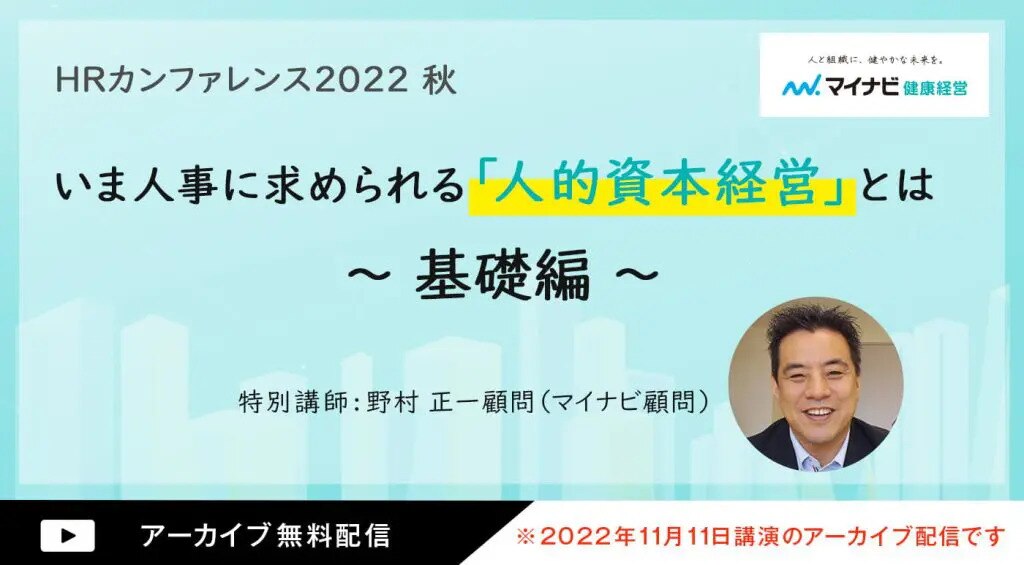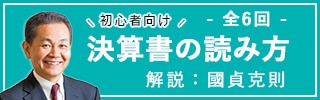用語集
あ行

ROI (リターン・オン・インベストメント)
2023-07-26
ROIは「Return on Investment」の頭文字を取った略称で「投資利益率」「費用対効果」などと訳されます。投資した費用に対してどれだけのリターンがあったのかを示す指標で、ごくシンプルな計算式は「利益÷投資額×100」です。ROIは財務関連を計る場合と、特定の施策に対する効果を計る場合に大別されます。

RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)
2023-02-16
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション:Robotic Process Automation)とは、人がパソコンなどで行っている定型的な業務を自動化する技術や取り組みです。

ROESG(アール オー イー エス ジー)
2023-07-26
「ROESG」とは、ROE(自己資本利益率)はESG(環境・社会・企業統治)を合わせた造語です。2つを用いて企業を評価するという概念、もしくは評価指標だとされています。

アンコンシャスバイアス
2023-07-26
アンコンシャスバイアスは通常、「無意識の偏ったものの見方」「無意識の思い込み」「無意識の偏見」などと訳されます。アンコンシャスバイアスは脳がエネルギー消費を抑えて物事を判断するための機能です。

EAP(Employee Assistance Program)
2024-03-28
EAP(Employee Assistance Program)とは、従業員支援プログラムのことを指し、企業が従業員とその家族のメンタルヘルスや生活問題に対する支援を行うための制度です。

ES(従業員満足度:Employee Satisfaction)
2024-01-31
ES(従業員満足度:Employee Satisfaction)は、従業員が自身の勤務環境や労働条件、人間関係、給与、キャリアなどにどれだけ満足しているかを表す指標です。

ESD(持続可能な開発のための教育)
2024-03-26
ESDはEducation for Sustainable Developmentの略で、「持続可能な開発のための教育」を指します。持続可能な社会の作り手を育てていくための教育です。
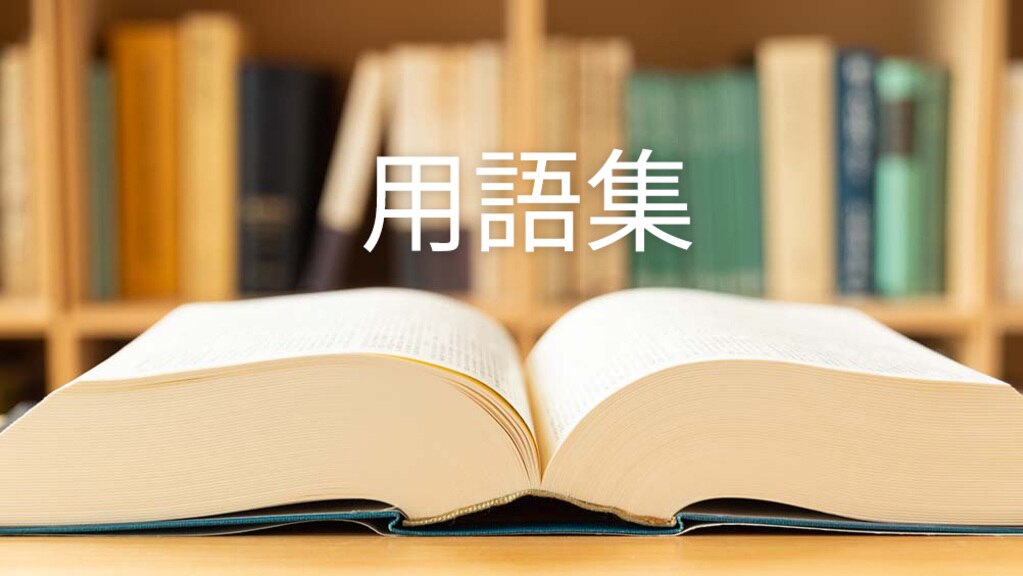
HRBP(HRビジネスパートナー)
2023-07-26
HRBP(HRビジネスパートナー)とは、企業の経営層と同じ視点で戦略的な人事目標を設定・遂行する人事のプロフェッショナルのことです。 HR(Human Resource)は人的資源を意味します。特定のポジションを指すのではなく、企業全体の動きや問題点を鑑みて人事面からアプローチする役割や機能を指すことが多いです。

ウェルビーイング経営
2023-12-28
ウェルビーイング経営とは、「従業員が肉体的・精神的・社会的に満たされている環境を社内に構築する経営手法」とされ、世界保健機関(WHO)憲章において、健康の定義として使用されたウェルビーイング(well-being)が由来といわれています。

エンゲージメントサーベイ
2023-06-20
一般的にエンゲージメントサーベイとはエンゲージメントを測定すること で、組織の状態を測定する組織サーベイ(調査)のひとつです。なお、調査そのものではなく、調査ツールを指すこともあります。

エンプロイー・エクスペリエンス
2023-06-14
エンプロイー・エクスペリエンスとは「EX(Employee Experience)」のことで、一般的には「従業員体験」と訳されます。具体的には従業員が企業や組織で体験する経験価値を表す概念で、求職活動から退職に至るまでのすべてのプロセスにおける体験です。

女性活躍推進企業認定「えるぼし・プラチナえるぼし認定」
2022-11-10
「えるぼし認定」は、2016年に施行された女性活躍推進法にもとづき、女性活躍に関する取り組みの実施状況が優良であるなどの要件を満たした企業が申請すると、厚生労働省から受けられる認定です。
か行

GX(グリーントランスフォーメーション)
2023-11-01
「GX(グリーントランスフォーメーション)」とは、経済・社会、産業構造をクリーンエネルギー中心に移行させるための経済社会システム全体の変革を指します。

健康スコアリングレポート
2023-12-08
健康スコアリングレポートとは、各健康保険組合の加入者の健康状態、医療費、予防・健康づくりへの取組状況などについて、すべての健康保険組合の平均や業態平均との比較データを見える化したレポートです。

健康経営優良法人認定制度
2024-05-28
健康経営優良法人認定制度は、経済産業省と厚生労働省によって設けられた制度です。従業員の健康を重視し、その向上に向けた取り組みを経営の中心課題として実施する企業を公に認定し、その取り組みを広く社会に対して示すことを目的としています。


健康経営優良法人中小規模法人部門
2022-04-19
健康経営に取り組む優良な法人を顕彰する「健康経営優良法人認定制度」における区分の一つ「中小規模法人部門」は、従業員数や資本金(または出資金)額が一定基準までの企業等が対象です。
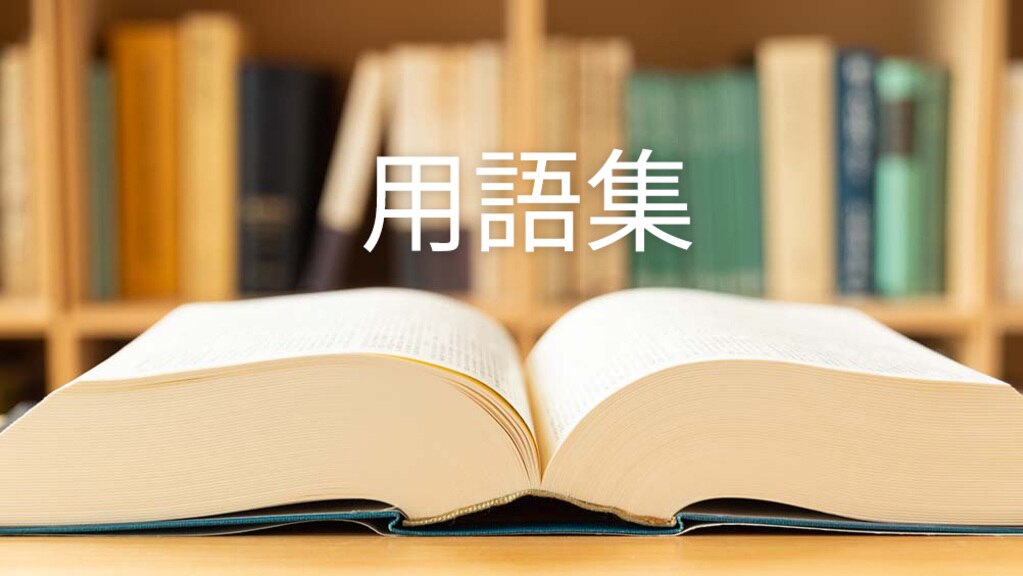
コーポレートガバナンス
2022-08-03
コーポレートガバナンスは日本語では「企業統治」と訳され、企業が株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等の立場を踏まえたうえで、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みです。
さ行

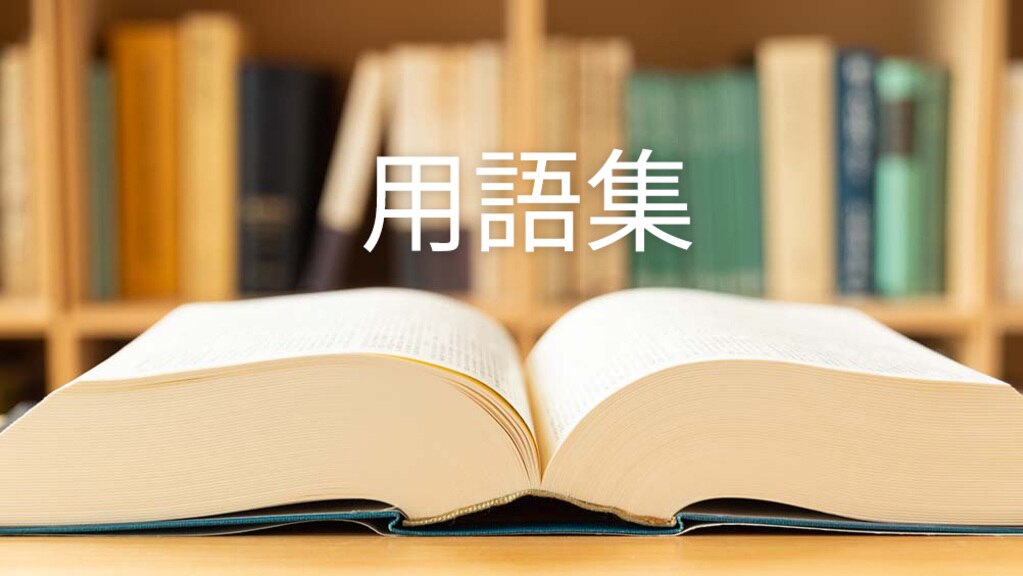
SX(サスティナビリティ・トランスフォーメーション)
2023-06-20
経済産業省によると、SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)とは「社会のサステナビリティと企業のサステナビリティを同期化させ、そのために必要な経営・事業変革を行い、長期的かつ持続的な企業価値向上を図っていくための取組 」と定義されています。
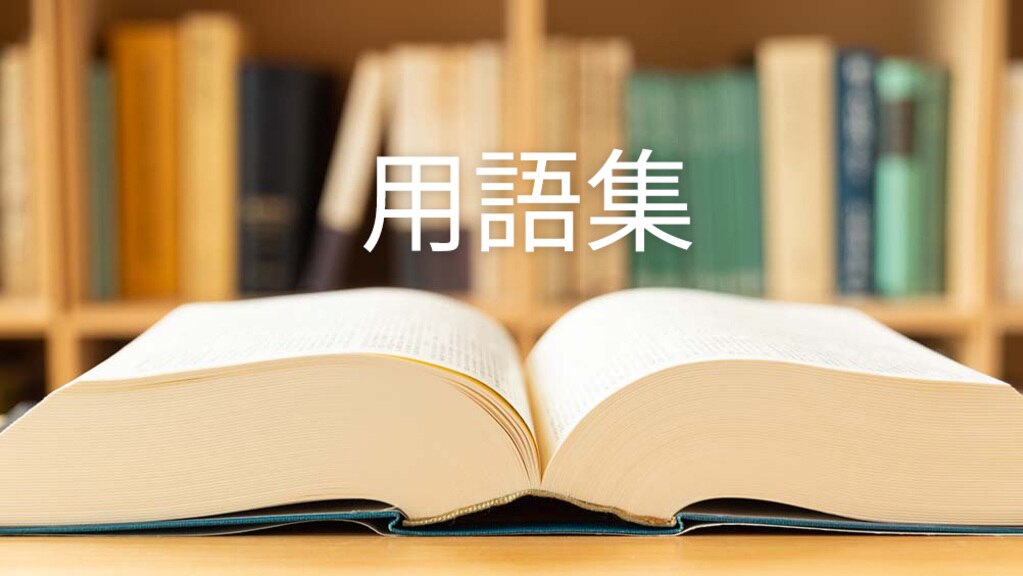
CSR(企業の社会的責任)
2024-03-28
CSR(企業の社会的責任)とは、企業が事業活動を行う上で、自社の利益だけでなく環境、社会、経済などの持続可能性を考慮しつつ責任ある行動と説明責任を果たすことです。

ジョブクラフティング
2023-06-07
ジョブクラフティングはWrzesniewski & Dutton(2001)によって提唱された概念で、論文では「課題や対人関係における従業員個人の物理的または認知的変化」と定義されています。
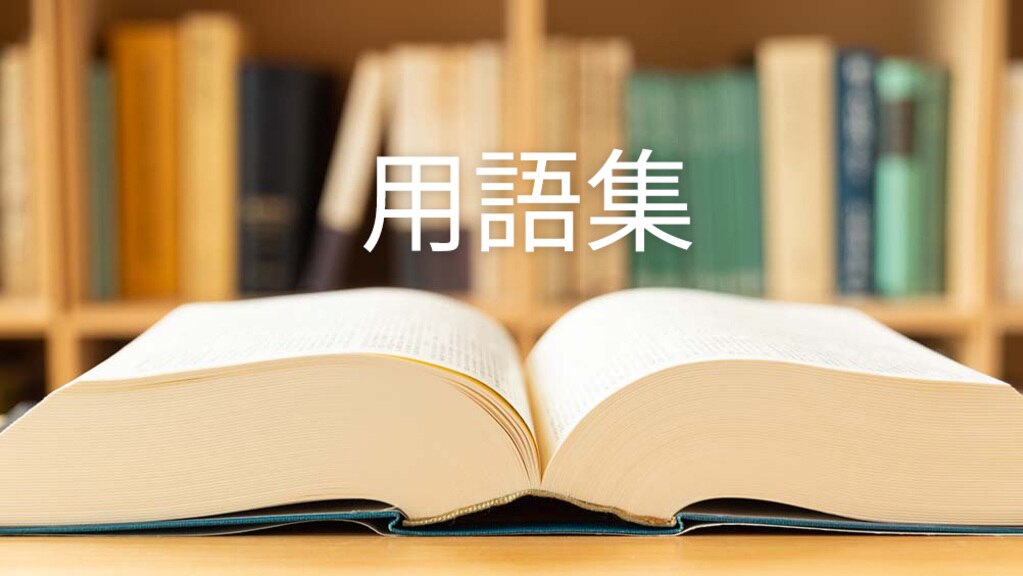
人的資本経営コンソーシアム
2022-11-01
人的資本経営コンソーシアムについて解説。人的資本経営コンソーシアムは、人的資本経営の事例共有、企業間協力の議論、情報開示の検討などを行う場として設立されました。

ストレスマネジメント
2023-12-26
ストレスマネジメントとは「ストレスとの上手な付き合い方を考え、適切な対処法をしていくこと」とされており、ストレス自体を防ぐ方法ではなく、ストレスを受けた際の対処法やストレスとの付き合い方を主に考えていく手法です。

スポーツエールカンパニー
2024-04-24
スポーツエールカンパニーとは、スポーツ庁が従業員の健康増進のためにスポーツの実施に向けた積極的な取組を行っている企業を「スポーツエールカンパニー」として認定しているものです。

ソーシャルキャピタル
2022-12-22
ソーシャルキャピタルは、アメリカの政治学者パットナムの著書において「人々の協調行動を活発にすることによって社会の効率性を高めることのできる、『信頼』『規範』『ネットワーク』といった社会組織の特徴」と明記されており、この定義が一般的に認知されています。
た行

トランジションファイナンス
2023-06-20
トランジションファイナンスは、省エネや燃料転換といったトランジション(移行)への取り組みに必要なファイナンス(資金供給)で、経済産業省によると「脱炭素社会の実現に向けて長期的な戦略に則り、着実なGHG(温室効果ガス)削減の取組を行う企業に対し、その取組を支援することを目的とした新しいファイナンス手法 」と定義されています。
は行

ハイリスクアプローチ
2023-12-12
ハイリスクアプローチとは、健診などでスクリーニングして疾病の発症リスクが高い人を特定し、リスクを下げるように働きかけることを指します。例えば、健康診断でメタボリックシンドローム予備群の人たちを早期に発見し、治療が必要な状態になる前に保健指導を徹底して、生活習慣の改善を促すアプローチです。

BCP(事業継続計画)
2023-02-03
BCP(Business Continuity Plan)は「事業継続計画」とも呼ばれ、自然災害やパンデミック、テロなどの事件や設備の事故のような緊急事態が起こったときに備えて、企業が事業を継続するための方法や手段を定めた計画を指します。
ま行
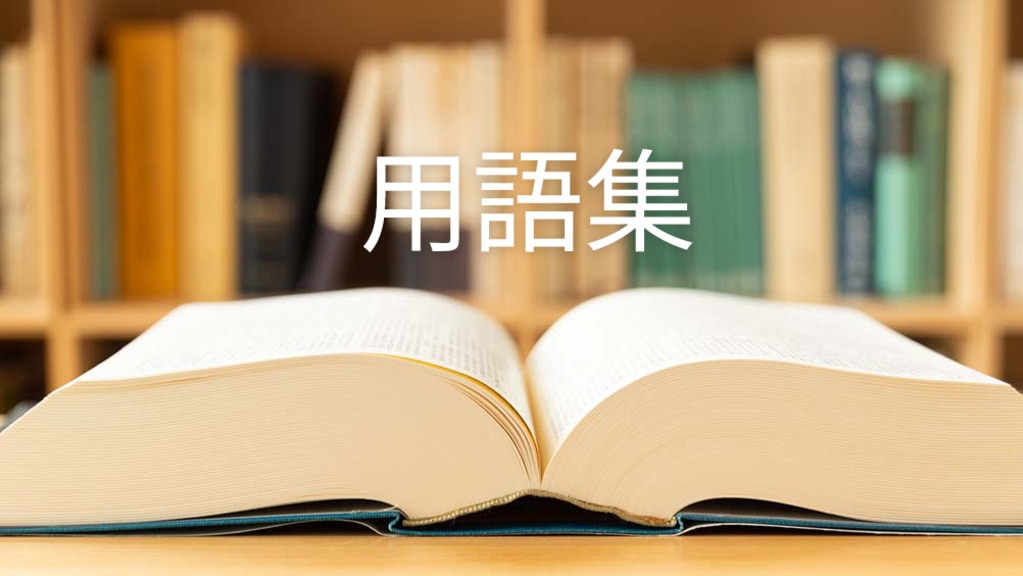
メタボリックシンドローム
2023-11-01
メタボリックシンドロームとは、腹腔内の腸間膜などに脂肪が蓄積する内臓肥満に、高血圧・高血糖・脂質代謝異常が組み合わさることで、心臓病や脳卒中などにつながりやすい状態のことを指します。
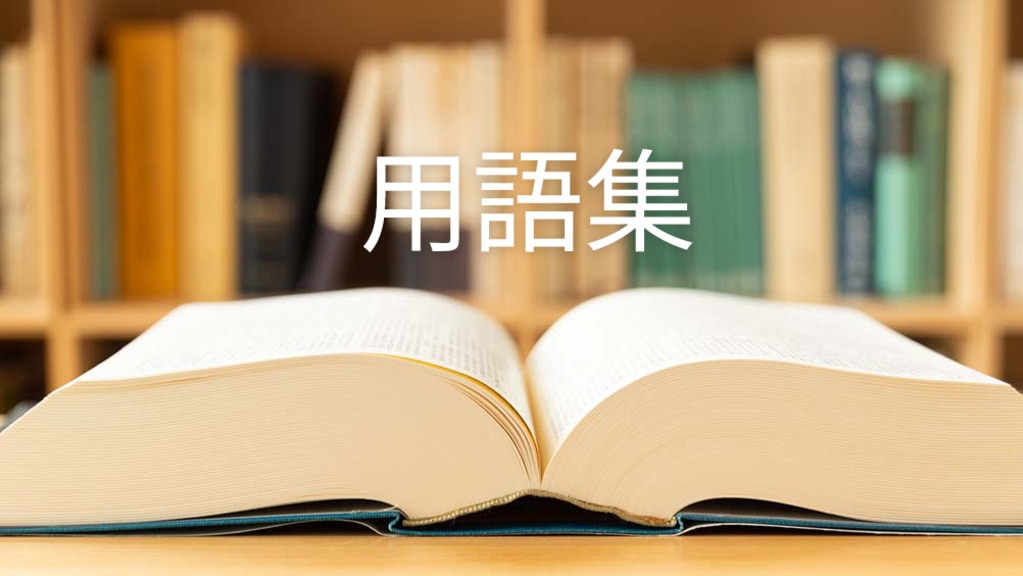
メンタルヘルスの4つのケア
2024-06-20
メンタルヘルスの4つのケアは、厚生労働省による職場における心の健康づくり「労働者の心の健康の保持増進のための指針」の中で、推進する対策として掲げられています。
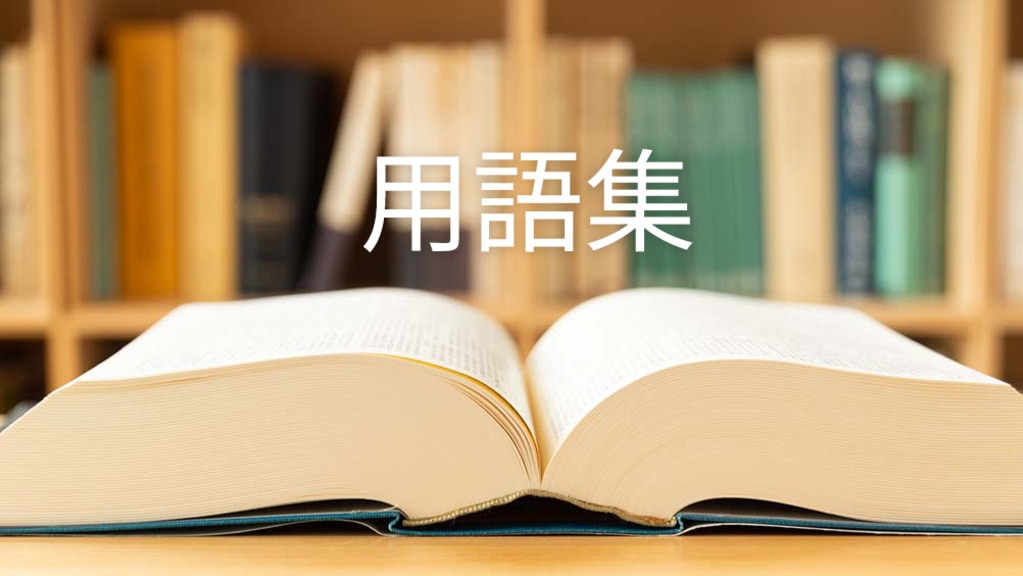
メンバーシップ型雇用
2022-08-01
メンバーシップ型雇用とは、職務内容を定めずに企業が総合的に判断して従業員に仕事を割り当てる、日本において一般的な雇用形態であり、新卒一括採用、長期・終身雇用、年功型賃金、異動・転勤を含む、企業内での人材育成といった特徴があります。
ら行
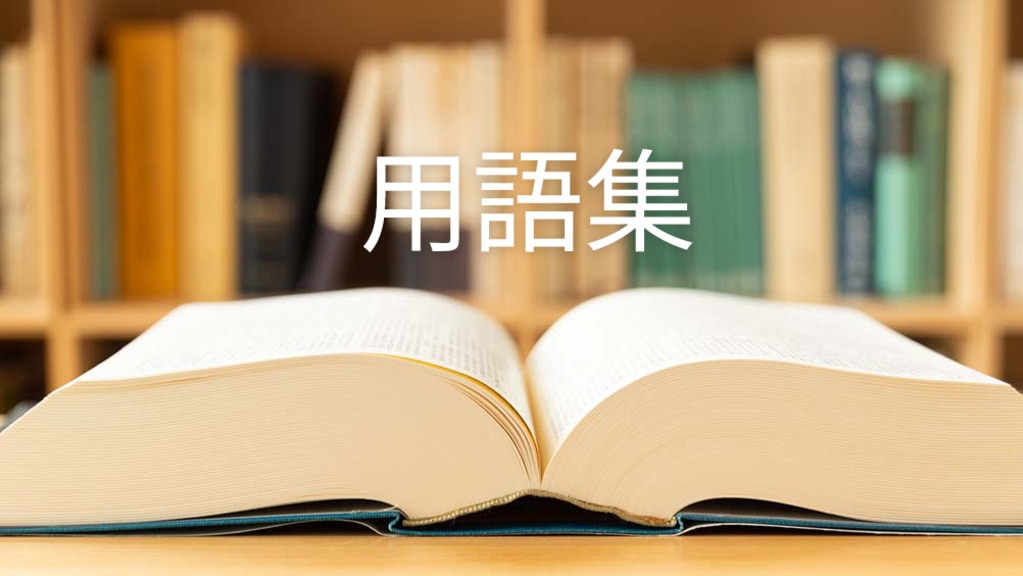
ロコモティブ・シンドローム
2024-02-27
ロコモティブ・シンドローム(運動器症候群)とは、加齢や運動不足を起因として、骨や筋肉、関節などの機能が低下し、歩行や日常生活に支障が出ている状態のことです。
わ行
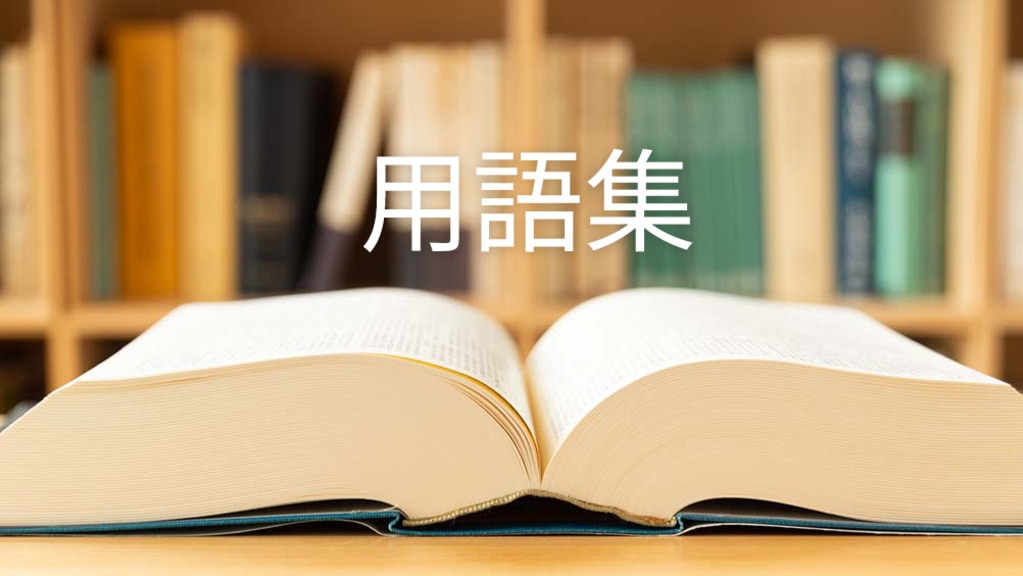
ワークライフインテグレーション
2024-02-27
ワークライフインテグレーションとは、ワーク(仕事)とライフ(プライベート)をインテグレーション(統合)し、「仕事」と「プライベート」両方の充実を図る考え方です。